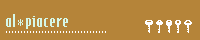菊花の約 (羽石司 / 原作:上田秋成)
青々とした、春の柳は、家の庭に植えてはならない。
交際は、軽薄な人間とするものではない。
川柳やしだれ柳は、茂りやすくとも秋の初風にはひとたまりもなく、散り行くものだ。
軽薄な人間は交流しやすくとも、離れていくのもまた早いのである。
楊柳は何度も春に染まるが、軽薄な人間はいつしか訪れる日もなくなるであろう。
播磨の国。加古の宿に丈部左門という学者がいた。
清貧を甘受する男だ。
友とし愛する書物のほかは、調度品がわずらわしく多いことを心底厭うような少々毛色の変わった男である。
また、彼には年老いた母がいる。
孟子の母はよりよい教育環境のために三度も転居したり、織っていた機の糸を刀で切って学問の中絶の不可を諭したりもしたものだが、彼女は麻などの繊維を寄り合わせることを仕事とし、左門の勉強する心を助けた。
ほかの家族は同じ里の佐用氏に縁付いている妹。
この佐用の家は大層富深いのだが、丈部母子の賢さを慕っていたが故に、彼女を娶ったのである。
ときどき何かにつけて物を贈りたがるのだがこの母子は「一家の生計のために他人の世話は受けられませぬ」とそれらを受け取ることはなかった。
ある日のこと。
左門は友人の家を訪問した。
昔話や最近の話などでおおいに盛り上がりちょうど面白くなってきたその時分。
壁を隔てた向こう側から、誰かが酷く苦しむ声が大変不憫に感じるほどに聞こえてきた。
すわ何事だと主に問えば、
「この地より西の国から来た方らしいが、連れに遅れたということで、一晩の宿を頼まれたのだ。
どうやら武士の風格があってとても卑しからぬ人らしく、泊めてやることにした。
ところがその晩、性質の悪い激しい熱にうなされてな。
起き上がることも自らではままならぬ様子でよ、
あまりに気の毒だったもんだから三日四日はここで過ごしてるんだが、
どこのどういう人物かもわからぬし、知らない人間を助けて失敗しちまったかと思ってんだ」
「お気の毒な話ですね。貴方が不安に思うのも、尤もな話です。
けれど病苦の人が知人もいない旅の空の下で苦しむのはとりわけ心の痛むことでしょう。
様子を、少し見せてくれませんか?」
「ちょっと待てよ。悪性の流行病は人を破滅させるものだっていうじゃねぇか。
家のやつらもあえてその部屋には立ち入らせぬようにしてんだ。
なにも自分から危険にさらされることもないんじゃねぇんかい?」
慌てた様子の主人に、左門は少し笑った。
「人の生死は天命によるもので、人力ではどうしようもないものです。
むしろ、何の病なのか、人に伝えるべきでしょう。
これらは無知なものの考えで、私どもは従いませぬ」
戸を押して入りながらその人を見ると、主が語ったのと違わず、普通の人物とも思えない。
ただ、病は重いと見えて、顔は黄色く染まり、肌は黒く痩せ、布団の上に悶えながら臥せっていた。
その人は存外親しみ深い表情で左門を見た。
「湯を・・・・一つ恵んではもらえぬでしょうか」
掠れた、病人の声だった。
どこか心細く揺れるそれに、安心させる笑みを左門は向けた。
「貴殿どうかご心配なさらず。必ず、お救いしましょう」
主と相談し、薬を選び、自分で処方を考えて、その手で煮て与えながら粥もすすめた。
その病を看る様はまるで兄弟のようで、本当に捨てては置けない手厚い看護ぶりであった。
その武士は左門のあまりの憐れみの厚さにいたく感激し、涙をこぼした。
「これほどまでに行きずりの者の面倒を見て下さいました貴公に、
死んでもこのご親切に報恩したしましょう」
「死んでも、などという心弱いことはおっしゃらないでください。
疫病は日数が決まっていて、その期間を過ぎれば生命に差し支えはないものです。
私が毎日参上して、看病しますから」
と大層誠実に約束し、こまやかに気遣いも左門は忘れなかった。
そのうちに病もようやく軽くなって気分が楽になったころ、武士は主人にも心からお礼の言葉を述べた。
左門が表立つでもなくしてくれた善行を尊敬した武士は、左門を訪ね、自らの身の上を語りだした。
「某、もともとは出雲の国の松江の郷で成人した、赤穴宗右衛門という者。
いささか兵法を会得しました故、富田の城主塩冶掃部介(えんやかもんのすけ)が某を師とし、
佐々木氏綱の密偵として選ばれ、佐々木の館にとどまり申した。
ところが前の城主尼子経久が大晦日の夜不意に城を乗っ取り、掃部殿も討ち死になさった。
もともと出雲は佐々木の国。
塩冶は守護代だったので『三沢・三刀屋を助けて、経久を滅ぼしてくれ』と氏綱に頼みなさったが・・・・
氏綱は一見勇猛だが実は臆病で愚かな大将、そうはしてくれなんだ。
かえって某を近江に留めた故理由もないところに長くはいられぬと身一つでそっと国へ帰る道中、
この病にかかり、おもいがけず貴公に世話になり申した。
身にあまる御恩、後半生の命をもって、かならずこの御恩に報いましょうや」
「人の不幸を見て捨てておけずに助けるのは人間の本来持っている心です。
深い感謝の言葉を受けるいわれなどございません。
もう少し滞在してご養生なさってください」
その優しい言葉を糧として日々を過ごすうちに、赤穴の体具合は常に近くなっていった。
いつしか顔色もよくなり、体を動かすこともできるようになり、話もはずむようになったのだ。
この頃から、左門はよい友を探し得たと、昼も夜も親しく語り合った。
赤穴も諸子百家のこともぼつぼつ語りだして、質問も理解力も優れた人物。
戦争の理論としての機略はとくに長じていたもので、ひとつとしてお互いに感情の行き違いもなく、
かつ感心したり喜んだりして、ついには義兄弟の契りを交わした。
赤穴のほうが五歳年長であったから兄であるべき礼儀を受け入れて、左門に向かって言った。
「某は、父母と別れて久しい。
我が賢弟の老母が即ち母であります故、改めてご挨拶申し上げたいと願いまする。
お母上は、子供っぽい我が心を受け入れてくださるだろうか」
「私の母は、常に自分の孤独を憂いております。
その信なる言葉を告げれば、寿命もきっと延びることでしょう」
と、左門は大いに喜び共に家へと帰った。
兄弟となった、二人の家へ。
老母は喜んで新たな息子を向かえ、笑顔を浮かべた。
「私の子は身に着けた学問が時勢に合わず、立身出世のつても失いました。
どうかお見捨てなく、兄者の教えを施してくださいませ」
「意志堅固な男は義を重んじます。
手柄も名誉も富みも地位もくだらぬことにございまする。
某は今、御母上の慈愛を受け、賢弟から兄として尊敬された、
それ以上の何の望みがございましょうか」
と赤穴は心底感激し、深く頭を下げた。
これにて、新たな家族が生まれたのだ。
昨日か今日咲いたと思った山上の桜もすっかり散りはて、
涼しい風の吹くのにつれて打ち寄せる波の気配にも、
訊ねなくともはっきりとわかる夏の初めが訪れた。
そんな、緑の濃くなる季節に赤穴は改まって母と弟に向き合った。
「某が近江を出たのも、出雲の動静を見定めるため。
故に一度出雲へ下り帰り、極めて貧しいもてなしながらもお仕え申したいと思う。
しばしのお暇をくださいませぬか」
「それならば兄上はいつお帰りになりますか」
「月日が流れるのは早いもの。遅くともこの秋より遅くはならぬ」
「秋はいつの日を定めて待てばいいのですか。どうか、月日を、約束してください」
「九月九日の節句に。その日を帰る日と定めよう」
菊の節句。
長寿を祝うその日にまた、酒を飲み交わそう。
重陽と言われるそのめでたい日に、再会を果たそうではないか。
そう、赤穴は笑った。
「兄上、どうかこの日を間違えないでくださいね。菊花と薄酒を用意して、お待ちしております」
と互いに誠実に約束して、赤穴は西へと帰った。
月日は早く過ぎ、下枝のぐみが色づき、垣根の野菊が美しく咲く、九月になった。
九日はいつもより早く起き出し、草葺の粗末な家を掃除した。
黄菊、白菊を二、三枝小瓶に刺し、財布をはたいて酒と飯の用意をした。
兄が帰るのを、心待ちにして。
息子の浮かれように、さしもの母も苦笑した。
「かの伊豆は山の向こう、ここからは百里もあるいいますよ。
今日と決めたからと言って、彼が着いてから準備をしても遅くはないでしょうに」
「赤穴は誠のある武士です。必ず約束は守ります。
当人がついてから慌てて支度したならば、彼がなんと思うか、私は恥ずかしいのです」
と言って良い酒を買い、新鮮な魚を料理して台所に用意した。
この時ばかりはほんの少し貧しい暮らしに頭を悩ませたのだが、精一杯のもてなしの準備は、整った。
この日は空もよく晴れ、見渡す限りどこにも雲がない旅日和であった。
里に行きかう旅人たちの声もはずむ。
「今日は与助が都入りしたらしいぜ。商売に上手い利益を得るのに吉兆だ」
と、空を眺めて男は笑った。
五十ぐらいの武士は、二十ほどの同じ服装をした武士に不満を漏らしていた。
「天気は快晴。船を雇っていたらこの早朝の船出で牛窓港へ風を受けて進んでいただろうに。
若いもんはかえって怯え、銭を多く費やすものだからいかん」
「殿が小豆島から室津を渡ったとき、散々酷い目にあったって従者が話しているのを聞いたら、
このほとりを渡るのに怯えて当然だろう? 怒るなよ」
馬の口を取る男は腹立たしげに
「この駄馬は目すら開けられないのか」
と、鞍の荷の形を整えて追っていった。
正午もかなり経過したけれども、待ち人は来なかった。
西に沈みゆく日。
通行人が宿を探して急ぐ足のせわしい様を何気なく見ていても、思うのはもっと外。
心が酔っていくようで、ただぼんやりと赤く染まる世界を眺めた。
「心が秋の空のように変わったわけではなくても、菊の色のように契り深いのは今日だけですか。
帰るという誠があるなら、時が過ぎて空は時雨模様に変わっても一体何を恨むことがありますか。
家に入って横にでもなって、また明日をお待ちなさい」
母に諫められては断れず家に入った。
母を納得させて先に寝かせたものの、やはり外へ出てみれば、
天の川にある星の光は朧朧で、冷たい月が自分のみを照らして寂しげで、
番犬の吼える声は澄み渡り、波の音もすぐそこまで打ち寄せて聞こえるようだ。
月の光も山の端に隠れるころには、さすがにこれまでと戸を閉め、入ろうとした。
そのときのことだ。
ふと見ると、朧な陰の中に人がいて、風が吹くのを不思議に思ってみると、赤穴宗右衛門だった。
左門は狂喜した。
帰ってきた、兄上が帰ってきた!
飛び上がる思いで駆け寄って、笑顔を向けた。
「お待ちしていましたら、こんな時間になってしまいました。
お約束に違わず来て下さったこと、嬉しく思います。さぁ、お入りください」
と言うようだが、赤穴は一つ頷くだけで、一言も物を言わない。
弟との再会に妙に表情が沈んでいる。
長旅で疲れているのだろうか。
左門は先に進んで、南座敷の窓の下へ向かい、座につかせた。
「兄上があまりに来るのが遅いものですから、母も待ちわびて明日こそと布団に入ってしまいました。
起こしてまいりましょう」
けれど赤穴は頭を振ってそれをとどめた。
相変わらず少しも物を言わない様子である。
「夜も昼も休まず旅を続けておいでになったので、心も足も疲れましたでしょう。
よろしかったら一杯呑んで、お休みなさいませ」
兄は疲れているのだ。
酒を温め、肴を並べてすすめた。
ところが赤穴は袖で顔を覆い、まるでその生臭さを嫌って避けているようである。
さすがに、左門の声が沈んだ。
「手料理で十分なおもてなしは出来ませんが、私の心遣いです。
どうか、召し上がってくれませんか?」
赤穴はなおも答えなかった。
長い長い息を吐いて、しばし経ってからようやく口を開いた。
「賢弟の誠あるもてなしをどうしてお断りできる理由がろうか。
嘘を吐く言葉もないので、事実を申す。決して怪しまぬようにしてくれぬか。
某はもはや、この世の人ではないだ。
穢れた霊が、仮に姿をあらわしたものなのだ」
「兄上、何ゆえそのような・・・どうしても、本当には思えません」
「貴殿と別れて国に下ったが、国人は多くが経久に従って、塩冶様の恩恵を顧みる者もいなかった。
従兄弟の赤穴丹治が富田の城にいるので訊ねたが、丹治は利害を説いて某を経久に会わせた。
仮にその言葉を受け入れて、よくよく経久の所業を見申したが、
万人にも当たる勇気に優れよく兵士を訓練するとも言えども、智者に疑い深い心を持っていた。
主君と心を一つにし手足となって働くような家臣もいない。
長くとどまっても益はなかろう。
賢弟と菊花の契りがあることを話し去ろうとすると、経久は丹治に命じたのだ。
某を富田の城から出さぬように、と。
ついに今日になってしまった。
約束をたがえてしまったなら、貴方は某をどんな人間と思われるだろうか。
一途に思い沈むけれども、逃れる方法は、ない。
けれど、古の言葉がある。
『人が一日に千里を行くことはない。だが魂は千里を一日で駆ける』
この道理を思い出し自ら刃を立て今夜、陰気な冷たい風に乗りはるばる菊花の誓いを果たしに参った。
どうか、この心を哀れに・・・・」
言葉の終焉には、最早涙がとめどなくあふるるのだ。
ただ、その赤穴の長い話を、黙って聞き続けた。
「今は長い別れになりまする。どうか、母上に孝行申し上げるように」
と、座を立つように見えたが、掻き消えてしまった
見えなく、なってしまった。
左門は慌てて留めようとするが、去る霊をのせた陰風のせいで眼がくらむ。
赤穴の行方もわからなくなってしまった。
うつぶせにつまずき、倒れたままの姿勢で、大声をあげて、哭いた。
あにうえ、と。
慟哭した。叫んだ。泣き叫んだ、失ってしまったことを。
これには母も眼を覚まし、驚いて立ち上がって、左門がいる場所を見た。
客席のあたりにさかなが盛ってある皿がたくさん並べてある。
その中に倒れ伏しているのを慌てて助け起こした。
「どうしたのですか?」
と問うが、ただ声を飲み込むように泣くばかりで一向に言葉がかえって来ない。
「兄赤穴が約束を違えたのを怨みに思うなら、明日こそ来たときには言うべき言葉もないでしょう。
お前はこれほどまでに愚かだと言うのですか」
く諫めると、左門はようやく母を見た。
はらはらと涙が頬を伝い、地に落ちる。
ちがう、と小さく唇が動いた。
「兄上は今夜、菊花の誓いにわざわざ来てくれました。
酒やさかなをもって迎えましたが、何度も辞退された上
『約束に背いてしまう故、自死して魂のみが百里を来た』
そう言って見えなくなってしまいました。
見えなくなってしまったんです!
いなくいなってしまった、兄上が、いなくなってしまった・・・・!」
最後に、押し殺すような声で、起こしてしまいすいませんでした、と搾り出した。
あまりに取り乱し涙を流す息子の頭をそっと撫で、母はつとめてやさしい声を紡いだ。
「牢獄に繋がれた人は夢に許されることを見ます。
のどの乾いたものは夢の中で水を飲むといいます。
お前もまたそういう類でしょう。落ち着きなさい」
けれども左門は頭を大きく振った。
最後に会った時と変わらぬ姿、とはいえぬ兄の姿。
顔色は悪く、憂いを帯びた表情、気配、魂。
けれども、その声だけはするりと己の中に入り、その存在を、確固たる意志を主張した。
「本当に夢のような不確かなものではないのです。
兄上はここに、本当にいらっしゃったのです」
とまた声を放り投げて哭いた。
母も今度は疑わなかった。
その慟哭は、夢では済まされない。
名を呼び合って泣いた。
夜を泣き明かした。
血の繋がらぬ、けれど確かな家族を悼んで。
翌日、左門は母に頭を下げて言った。
「私は幼いころから学問文事に心を傾けてきました。
けれど国に忠義の評判もなく、家に孝心をつくすこともない。
、悪戯にこの世に生きているだけです。
兄上赤穴は一生を信義のために終えました。
弟の私は、出雲へ下りせめては遺骨を葬って信義を全うしたい。
母上、どうかお体をお大事にしてくださって、しばらく暇を」
「私の子、何処へ去るとしても早く帰って年を取った私を安心させておくれなさい。
長くとどまって、今日を永遠の別れの日とすることのないように」
「人間の生命は流れに浮かぶ泡沫のようなもの。
朝に夜に消えるときを定めがたくとも、まもなく帰ってまいりましょう」
流れる涙を拭った。
家を出ると、佐用氏に老母のことを懇ろに頼み、一人左門は歩いた。
飢えても食欲が湧かず、寒くとも衣を必要とせず、眠っている夢の中でも慟哭した。
兄のことだけを想った。
そして、十日を経て富田の城へ至った。
まず赤穴丹治の家へ行き、名前を告げて案内を乞うた。
契りの話をしていたのだから、当然丹治もそれを受け入れた。
「鳥や雁が告げるのでもなくて、どうしてお知りになりましたのか、不思議なことです」
としきりに問うてきた。
どうして、その言葉はこちらが叫びたい言葉だ。
「武士たるものは財産に富み、位が尊くとも、栄枯盛衰について論ずるべきではありませぬ。
ただ、信義のみを重く。
兄宗右衛門は一度した約束を重んじ、なくなった魂で百里を超えることで報いとしました。
私は夜を日についで急ぎ、ここへ参りました。
私が学び知ったことで、貴君にお尋ねしたいことがあります。
どうかはっきりとお応えください」
ひとつ、息を吐く。
そう、あの人は義だけを、重んじた。
己が命よりも何よりも、弟との約束を重んじた。
「昔、魏の公叔座が病のため床に伏したときに、魏王自ら見舞い、手を取って次げました。
『万一死が迫ったならば、誰をして国家を守らせればよいのだ。私のために、教えを残してくれ』と。
叔座は『公孫鞅はとし若いといえど、奇才がございます。
王がもしこの人をお用いにならないなら、これを殺しても国境から出してはなりませぬ。
他の国へ行かせたなら、必ずや後に災いとなるでしょう』と答えました。
このこと、貴公と宗右衛門と比べてみてはいかがですか」
決して詰問するような口調ではない。
淡々と、そうまるであの日口をつけられなかった菊酒のように。
丹治は、頭を垂れて言葉もなかった。
左門はここで、身を乗り出した。
「兄が塩冶殿との古い交際を思い、尼子へ仕えなかったのは義を重んずる武士だからです。
貴公は、旧主の塩冶殿を捨てて、尼子に下って武士の義理を全うしていない。
兄上は菊花の契りを重んじて、命を捨てて、百里を超えた。
その信義を重んじる心、どれほどのものですか。
あなたは今尼子に媚びて肉親を苦しめ、非業の死をさせたこと、友とする信義がありませぬ!
経久が無理に止めようとも宗右衛門への古い交わりを思えば商鞅叔座の誠を尽くすべきだった!
ただ栄達と利益にのみ走り、武士としての気風がないのは、即ち尼子の家風でしょう。
そんな地に兄上はどうして、足をとどまれますか。
義を何よりも重んじた兄上が!
私は今その信義を重んじてわざわざここにいます。
貴方はまた、不義のために、汚名を残しなさいませ!」
と言って鞘から抜いた刀を構えずすぐに打つと、その一刀で丹治は倒れた。
家来どもが立ち騒ぐうちに早々と逃れて、もはや跡形もなかった。
尼子経久はこのことを伝え聞き、兄弟の信義の篤さを哀れに思い、左門の跡を追わせなかったと言う。
ああ、軽薄な人と約束を交わしてはいけないというが、まったくそのとおりである。