|
※ストーカー、監禁などの表現がありますが、それらを推奨する意図は一切ありません。 ※とにかく不健全で暗いヤンデレです。自己責任でお読みください。 その男は、ある日ふと思い出した。「今ここにある己の命」が、誰のために存在しているのかということを。  目を覚ました時、は知らない部屋にひとり横たわっていた。 「……あれ、」 ―――ここ、どこだろう。見知らぬ部屋の硬質なベッドの上で真っ先に浮かんだのは、戸惑いと疑問だった。 は、この場所がどこであるのか、そしてこの場所に自分がいる理由に少しも心当たりがなかった。見知った空間でもなければ、自分の意思で足を踏み入れた覚えさえもまるでない。 さらに奇妙なことに、彼女の記憶からは、「この場所で目を覚ます直前まで、自分がどこで何をしていたのか」という情報さえも失われていた。自分自身の名前や勤務先などの記憶は全てあるにもかかわらず、今日が何月何日で、さっきまで自分がどこにいたのかを思い出すことができない。当人は気付いてはいなかったが、彼女の脳内では一時的な記憶の混濁が起こっているのだった。 茫漠とした不安と共に彼女を襲ったのは、普段の寝起きには感じぬほどの倦怠感だった。何故だか頭からつま先まですべてが重く、ぬるま湯のようなまどろみから意識を引き上げることにもいささかの時間を要する。彼女は、まだ思考もうまく働かないままに、焦点の合わない目で周りをひととおり見渡した。 室内は広く、天井も高い。頭上に備え付けられた電燈の光は、部屋の隅々までを明るく照らしている。一見すると解放感溢れるような空間ではあるものの、この部屋には閉塞感を感じさせるいくつかの奇妙な点があった。 彼女がまず第一に気が付いたのは、自身を取り囲むものがすべて白に統一されていることだった。それは天井から壁一面に至るまで、さらには据え置かれた僅かな数の家具もまた同じだった。三百六十度、どこに目を向けても、彼女の視界には色が生まれ得ない世界が築かれている。 気付いたことはもう一つある。これだけの広さがある空間にも関わらず、窓が一つも設けられていないのだ。さらに、時計やテレビなども置かれていない。 そう。この空間には、が外界との繋がりを確かめられる媒体の一切が、あらかじめ排除されていた。彼女がこの非現実的な空間から脱し、現実に帰ろうとするのを、頑丈な鎖で繋ぎとめるかのような周到さで。まるで、生まれた時からここにいたのだという錯覚を植えつけんとするように。何者かの意志によって。 は、自身の身体が急速に底冷えていくのを感じた。 この場所は、異常だ。 拉致、監禁、殺人。いつかフィクションで見た、閉鎖的な施設のような空間の中で、脳裏には次々と物騒な想像が浮かんでいく。は、己の脳が打ち鳴らす警鐘に従い、すぐさま立ち上がろうとした。 しかし次の瞬間、彼女は絶句する。自分の身体を支えようとした腕に、全く力が入らないのだ。全身にこびりついた倦怠感は知覚していたが、いざ四肢を動かしてみると、手足は完全に痺れきりほとんど動かない状態だった。代わりに大声を出そうとしたものの、喉元が僅かに振動するのみで、まともな言葉すらも発せずに終わる。 色も音も存在しない空間で、ひとり自由を奪われたは、やがて声もなく泣き出した。彼女のすすり泣く音をかき消すものは何もない。ただただ圧倒的な静けさだけが横たわっている。空調音さえも、息をひそめて耳を澄まさなければ聴こえないほどだった。 が背にした向こう側には、白く大きな扉がある。 重々しく佇むその扉の外側に、得体の知れない何者かが立っている光景を想像すると、彼女は怖くて怖くて堪らなくなった。  「さん」 ―――どれだけ時間が過ぎたかもわからない。何も考えられない。やがて自分の意識がゆるゆると溶けだして、自分を取り囲む真っ白な壁と融合してしまいそうだと錯覚し始めたころ、聞き覚えのない男性の声がの脳を揺さぶりおこした。 「目が覚めましたか?」 声のするほうへ顔を少しだけ傾ければ、重そうな扉を背に、長身の男が立っている。それは、濡れ羽色の髪を持つ若い青年だった。病的なほどに目を焼く真っ白な空間の中で、ようやく彼女の視界に色が生まれる。まるで彼自身が、無地のキャンパスにぽつんと描かれた絵のようにも見えた。 「すみません。少々外出していたのです。目を覚ました時のために、さんの好きなものを沢山買い込んできましたよ」 「―――だれ、」 思わず口から零れたその言葉に、男は一瞬だけ動きを止めた。そして、目を見開いて彼女を食い入るように見つめたが、やがてふっと微笑んで、ディルムッド・オディナと名乗った。 ディルムッド・オディナ。顔を見たこともなければ、名前にさえも覚えがない。その事実は、の精神を、より一層心もとない不安に溺れさせた。閉口した彼女が、次に返す言葉を必死に思索していると、男ーーディルムッドの垂れ目がちのまなじりが、さらに緩く弧を描く。 「……ああ。すみません、これではわからないのも当然ですね」 その言葉が意図するところが知れず、なおも不安そうなまま黙りこくるに向き直ったディルムッドは、突然自らの前髪を大胆にかき上げた。男性のものにしては長めの前髪が、一気に後頭部へと流され、彫りの深い顔の造りがより露わになる。 「あなたにとっては、こちらのほうが見覚えがあるでしょう」 そして口を閉じたまま、息だけで笑う。肌を柔くくすぐる羽根のようにこそばゆく、丸みを帯びた笑い声だった。 男は「見覚えがあるでしょう」と言った。しかし、さも旧来の知人のように振る舞うこの男の存在にも、彼の口にする言葉の意味にも、にはさっぱり思い当たる節が存在しなかった。ウェーブのかかったの髪も、蜂蜜を流し込んだような琥珀色の瞳も、何もかもが初めて出会うものだった。 「あなたの様子を何度も見に来ていたんですが、一向に目を覚まされないので、心配していたんですよ」 そんなの戸惑いをよそに、ディルムッドはなおも優しげな微笑を彼女に向ける。こんな特異な環境でもなければ、今すぐにでも心を開き、信じきっていただろう。それほどまでに、警戒心を抱かせぬ穏やかな表情だった。優しげに垂れ下がった目元は、見る者に安心感を抱かせる。 けれど。 無機質かつ閉鎖的、非現実的な状況下で、この男は笑っている。状況の説明も一切せず、それが自然であるかのように話しかけてくる。 明らかに異様だった。この、ほんの数回の言葉のやりとりだけで、彼の異常性を察するには十分だった。この男は決して自分を助けに来た人間ではないということを、は痛いほどに察し取っていた。 「…ここは、」 先ほどとは違い、今度こそはっきりと声を出すことが出来た。手足も自由に動かせる。そのことに僅かばかり安堵しながら、彼女は意を決してディルムッドを見上げる。 「ここは…どこですか?私、なんでここにいるんですか?」 それは、ともすればこの状況を一気に悪化させかねない問いかけだった。次の瞬間には殴られるかもしれない、怒鳴られるかもしれない。は、血の気の引くような思いで両手を握り締め、恐怖に捉われる己を奮い立たせた。 しかし、彼女の恐れに反して、怒声や痛みは待てども襲ってこない。 恐る恐るディルムッドの表情を伺い見ると、彼は決して怒る素振りもなく、ただただ不思議そうに首を傾げていた。その表情があまりにも毒気の抜けたものだったので、は思わず安堵の息を吐いた。自分と彼との反応の温度差に、半ばもどかしい気持ちを抱えながらも、出来るだけ相手を刺激しないような静かな声音で、同じ問いをもう一度繰り返した。すると、彼はなお理解ができないといった様子で、今度は呆れ混じりの表情をつくり微笑んだ。まるで、聞き分けのない幼児を諭すような眼差しだった。 「なぜ、そんなくだらないことを質問なさるのです?」 毅然としたその視線にはあまりにも迷いがなく、さも当たり前とだ言わんばかりに堂々としたものだったので、は逆に怯んでしまう。それどころか、間違ったことを言っているのは自分のほうなのだろうか、という錯覚にさえ陥りそうだった。その一瞬の隙に、ディルムッドはなおも温厚そうな笑みを浮かべたまま、矢継ぎ早に言葉を並べていく。 「ここにいるのは、あなたと俺の二人だけ。その他に、何か重要なことなどありますか?それ以外は、取るに足らない些末なことじゃないですか」 流れるように告げられたその台詞の中で、「二人だけ」という言葉が、の心臓をにわかにざわつかせた。ディルムッドは、ただ彼女を見下ろして笑っている。その表情は確かに穏やかだったが、どことなく心にねっとりと絡みつくような、気味の悪い笑みだった。 「俺はただ、あなたとの"約束"を果たしに来ただけですよ」 ―――いったい、何を言ってるんだろう。 の中の警戒心が、より一層、ぞわりと粟立った。彼の温厚そうな容姿に釣られ、どうにか話が通じるかもしれないと一瞬でも淡い期待を抱いた心は、あっけなく打ち砕かれた。 「あなたなのね?」 喉から絞り出した声は、恐怖で震えていた。 「私を、ここに連れてきたのは」 彼は一切の表情を変えぬまま、何も言わず薄く微笑んでいる。その沈黙こそが答えなのだと、はそう直感した。 「……帰してください」 「あまり感情を荒げては、お身体に触ります」 「やめて!」 こちらに近づこうとするディルムッドの動きに身構えたは、思わず金切り声をあげ、自らの肩に伸ばされた彼の腕を力いっぱいに振り払った。先ほどまでとは打って変わった大声に、ディルムッドは驚いた様子で瞬きを繰り返す。 「これは手厳しいですね」 振り払われた手の甲を愛おしそうに撫でさすった後、臆することもなく、にんまりと目を細めて笑った。 「……どうやら、思っていたよりも薬の効き目が短かったらしい」 呼吸が止まりそうになった。 ぞわりと、何かが一瞬で背中を這うような衝撃の後、気付けばは扉へと駆け出していた。ひやりと冷たいノブに手をかければ、あれほど重そうに見えた扉は、彼女の力でも容易に開けることができた。 そして、もつれるように廊下へと飛び出した後、は後ろを振り返ることなく、無我夢中で走り出した。  その男は、ある日ふと思い出した。「今ここにある己の命」が、誰のために存在しているのかということを。 十月十四日、後にこの日は、彼にとっての忘れられない運命の日となる。 それは天啓の如く突然に、そして雷のような衝撃をもって、彼の全身を容赦なく貫いた。 その日、彼――×××が隣町の市民図書館まで足を運んだことは、ほんの小さな気まぐれだった。 本が読みたい。仕事で携わっていたプロジェクトが一段落したことで、生活や心身ともにゆとりができたばかりの彼は、ふと、そんな漠然とした思いに駆られた。元々、読書は昔からの彼の趣味の一つだったが、大学を卒業し、会社に勤め始めてからは、そんな趣味からもしばらく遠ざかっていたのだ。 何が目当てでもなかった。ただ書棚を眺めて、興味の惹かれるものを何冊か手に取れればいい。そんな軽い気持ちで、彼は、最寄駅よりさらに二駅先にある図書館へと足を運んだのだった。 そこで、彼女に出会った。 厳密に言えば"出会った"というよりも、"見つけた"という方が正しいかもしれない。あるいは、"気付いた"とでもいうべきか。 彼が数冊の本を抱えて貸出コーナーへと向かう頃には、館内に残る人の姿もほとんど見当たらなかった。また、閉館時刻が近いためか、その時カウンターにいたのも、年若い女性のスタッフ一人だけだった。 女性の背後に掛けられた壁時計を見上げつつ、焦りながら本を手渡すと、彼女は一冊一冊丁寧にバーコードを読み取りながら控えめに笑い、「そんなに慌てなくても大丈夫ですよ」と言う。凛とした大きな瞳が印象的な、大人びた顔立ちの女性だ。しかしその声は存外高く、彼の耳に柔らかく馴染んだ。ふわふわとした栗色の髪は、その白い肌によく映えている。 彼は少しばかりの気恥ずかしさを感じながらも、彼女の手から本を受け取ろうとした。 そして、ほんの一瞬、自分と彼女の指先が触れ合ったのだ。 次の瞬間、彼はすべてを思い出した。 自分の魂が、一人の女性のために存在しているのだということを。 その女性こそが、目の前に座る栗色の髪の彼女だった。 何故、忘れていたのだろう。こんなにも、何よりかけがえのない記憶を。彼女との思い出のすべてを。×××として生を受ける以前、自分は「ディルムッド・オディナ」であり、また、ランサーの名を冠する英霊の一人であったこと。ここではない世界で、その女性を守る存在として生きていたこと。そして、彼女が最期に残した言葉と、自分が立てた誓い。 それらの記憶は、一瞬で彼の全身を駆け巡り、しばし彼をその場に立ち尽くさせた。しかしそれもほんの数秒のことで、彼はすぐに我に返り、自分を気遣うように顔を覗き込んでくる女性の右手と、エプロンにつけられた名札を素早く確認する。 ―――。それが、小さなプラスチックのプレートに刻まれた彼女の名前だった。咄嗟に右手に目をやってしまったのは、ほとんど条件反射のようなものだった。彼女の手の甲は白くなめらかで、無論、赤く刻まれた紋章などどこにも存在しなかった。 帰宅した後、彼はスーツの上着を脱ぐことも忘れてベッドに倒れ込み、音もなく静かに泣いた。何故、忘れていたのだろうか。自分にとって彼女はすべてであり、決して忘れてはならない存在だったはずだ。彼の胸の内には、二十数年ものあいだ、彼女のことを忘れのうのうと生きてきた己に対する自責の念と、彼女との記憶を取り戻した幸福感とが、嵐のようにせめぎ合っていた。 彼がすべてを思い出すことができたのは、ただの偶然にによる出来事だったのかもしれない。しかし彼自身は、それを必然と疑わなかった。 ―――これを運命と呼ばずして、なんと呼ぼう。 それから×××は、彼女に気付かれぬよう、ひっそりと図書館に通い始めた。 彼女はあの世界の記憶を持っていない。すなわち、もはや別人としての人生を歩んでいるのだ。彼はそれをわかっていた。それでも、すべてを思い出してしまった以上、彼女の魂を受け継ぐ人間がこの世に存在しているという事実そのものが、昼夜問わず彼の精神を揺さぶった。彼女の存在に見て見ぬふりをすることなど、到底出来るはずもなかった。 「」として生を受けた彼女の容貌は、当然ながらあの世界での彼女のものとは異なっていたが、唯一瓜二つだったものがある。それは瞳の色だった。彼女の持つ双眸は、周囲の人間と比べて色素が薄く、薄められたキャラメルのような色をしている。大きくぱっちりとした瞳の形もあいまって、その色味はより一層強く目を引いた。彼はその瞳を見るたびに、あの世界での彼女の記姿を鮮明に思い起こすことができた。 毎日とはいかずとも、それなりの頻度でひと月も通いつめれば、彼女についての情報はある程度把握することができた。 この図書館には、アルバイトとしてではなく、司書として勤めていること。つい先日までの自分と同様に、前世の記憶を一切持たない身であろうこと。そして様々な人に囲まれ、幸せそうに日々を送っているということ。仕事終わりの彼女の行動を追っていると、時に友人と待ち合わせて食事に行くこともあれば、仲のよさそうな男と肩を並べて歩いていることもあった。 ――ああ、この人は、本当にすべてを忘れてしまっているのか。 なんて不幸なことだろう。それが彼の抱いた率直な想いだった。 彼女は、誇り高き偉大な魔術師だった。血統、センス、先天的な才能。それらのすべてに恵まれてなお、決して驕り高ぶらぬ天才だった。幼少期から何よりも魔術に没頭し、そのために自身の心血を注いできた女性だった。 そんな彼女が抱いていた魔術への情熱が、あれほどの類稀なる才能が、忘れられていいはずがない。記憶を取り戻すことこそが、彼女にとっての幸せなのだと、彼は疑いもなくそう確信した。 その瞬間、彼は、「×××」というひとりの人間としての人生を捨て、「ディルムッド・オディナ」として生きることを決意した。彼女に誇りを思い出させるために。彼女と交わした約束を果たすために。その選択に何の迷いもなかった。彼にとって、彼女こそが世界のすべてであり、あるいは世界のすべては彼女だったからだ。 それに気付いてしまったが最後、彼が成さねばならぬことは、もはや一つしか存在しなかった。  部屋を飛び出したは、目の前の光景に絶句した。 彼女の目の前には、どこまでも灰色のコンクリートの壁が続く、だだっ広い廊下が広がっていた。道は左右両方に向かって遥か遠くに伸びており、この施設がいかに広大なものであるかが窺い取れる。もはや一個人の住宅などではなく、巨大な敷地に鎮座する博物館を思わせるほどの規模だった。 頭上高くに仰ぐ天井にはところどころ窓が設置され、そこから差す自然光が淡く廊下を照らしている。先ほどまでは時間が把握できなかったが、どうやら今は陽の明るい時間帯らしい。しかし、あたり一面を覆い尽くす重々しい壁面のせいで、建物全体には、昼間とは思えぬほの暗さが漂っている。 は、自分が先ほどまで閉じ込められていたあの部屋を飛び出せば、この建物から逃れるための出口が見つかると思っていた。しかし、目の前に続く廊下の壁には、一切のドアが見あたらない。時折、曲がり角のようなポイントが見えるのみで、あとはただまっすぐな廊下が続いているだけだった。彼女の希望は、容赦なく摘み取られてしまいそうになる。 しかし、そんな動揺もつかの間、背後で扉が開く音がして、はふたたび弾かれたように走り出した。考えている余裕などなかった。とにかく、彼から逃げなければいけない。 手を振り払ってしまった。あの部屋を飛び出してしまった。きっとあの男は怒っているに違いない。自分を連れ戻そうと追いかけてくるに違いない。ひとたび捕まってしまえば、今度こそ命が脅かされるだろう。そう思うと震えが止まらなくなった。絶対に捕まってはいけない。悲鳴を上げる両足を叱咤し、彼の姿が見えなくなるまでただ走り続けた。 やがて彼女は、その奇妙な違和感に気付く。 走れども走れども、目の前にはただただ先の長い廊下が延々と続くばかりで、終わりが見えないのだ。どんなに目を凝らしても、幅の広い灰色の廊下が横たわるだけだ。階段や曲がり角にも何度か出くわしたものの、そこを抜ければ、また先ほどと同じ風景が広がっているだけだった。そのため、自分があの部屋の位置からどれほど進んだのか、あるいは、同じ道をぐるぐると走っているだけなのかということさえも、一切わからなかった。――そんな時だった。 『―――さん』 突然、ディルムッドの声がどこからか降り注いでくる。はびくりと肩を強張らせ、恐怖に震えながらも、自分が来た道を振り返った。けれどそこには彼の姿はない。 『――しばしお待ちください、すぐにあなたを迎えに行きますから』 ふたたび声がする。自分のものではない靴音と共に頭上から響いてくる。 ―――カツン、カツン、カツン。 コンクリートを打ち鳴らす足音は、規則的なリズムを刻みながら彼女の耳へと届く。それは遥か高い天井や硬い壁面に反響し、あらゆる方向から聴こえてくる。彼の声に全身を包まれているようで、ひどくぞっとした。ありえないとは分かっていながらも、あの男に四方八方から見つめられているような感覚に陥る。 なんとかして、彼の目からも、彼の声からも逃れたい。 そう思い、ひとまずディルムッドの声がする方向を突き止めようと、あたりに視線を漂わせたその瞬間、足をもつらせた彼女の身体は容赦なくコンクリートの床に叩きつけられた。痛みに顔を歪めながらもすぐに立ち上がろうとするが、張りつめられた緊張の糸が一気に切れてしまったのか、両足にうまく力が入らない。 「…っ、」 遠くに響き続ける足音を聴きながらも、どうすることもできない。の目からは止め処ない涙がただただ溢れ続けている。彼の姿はまだ見えないが、いずれここにたどり着くだろう。それまでに、なんとかして立ちあがらなくては。 「――ゲームオーバーですね」 先ほどまでは、居なかったはずなのに。 背後から、背筋を這うような低音の声が響き、は瞬時に後ろを振り返る。そこには、息も乱さず、汗ひとつかかず、涼しげな顔でこちらへゆっくりと近づいてくるディルムッドの姿があった。自分の血の気が一気に引いていくのを感じながら、は信じられない思いで首を振る。だって、さっきまで、どこにもいなかったのに。音もなく現れたこの男に対する恐怖は、より一層深いものとなってゆく。 「そういえば、あなたは昔からゲームがお好きでいらっしゃった。よく相手をさせられたものです」 「何を、言ってるの…?」 ディルムッドは何も答えない。口を開く代わりに、笑いながらの方へと歩みを進めてくる。 「来ないで、怖い…!」 「…怖い?」 青ざめるを見て、怪訝そうに首をかしげながらも、彼はどこか楽しそうに目を細めている。 「俺のことが怖いと仰る」 「助けて、嫌、死にたくない…!」 「…よもや、俺があなたを殺すとお思いではあるまいな?本当に面白いお方だ! 俺は、あなたを傷つけるすべてのものからお守りできる、唯一の存在だというのに!」 とうとう彼女の目の前にまで歩み寄ったディルムッドは、弾かれたように笑い声を上げた。それが純粋な面白みからではなく、彼女を滑稽に思う気持ちと憐れみにより引き出された笑いだということは、自身も十分に感じ取っていた。戸惑う自分をよそに、大層おかしそうに笑い続けるディルムッドの姿を、彼女はなおも恐怖に満ちた瞳で見つめていた。 しかし、彼はひとしきり笑ったあと、やがて先ほどまでの行動が嘘のようにすっと表情を失くして、静かに呟いた。 「―――本当に忘れてしまったんですか」 怒りとも悲しみともつかぬ表情を浮かべながら、ディルムッドはぽつりと呟いた。突如として急変したその様子に、は更にその身を縮ませる。 「思い出せない?本当に?」 先ほどよりも語気を強めて、念を押すように、ディルムッドは口早にそう言った。幾分か低められた声音は、先ほどまでの柔和さから一転した威圧感をに与える。けれど一方で、彼の視線からは、幼子が親に縋りつくような懇願の色も感じられた。そのあまりの悲痛さは、を、自分が悪いことをしているような気持ちにさえさせるほどのものだった。 今度こそ暴力を振るわれるかもしれない。いよいよ彼女の脳裏には、命を脅かす危機の予感が現実的なものとしてよぎり始めていた。 「……あなたは。――××殿は、本当に素晴らしい魔術師であられた」 ××。どうやらそれが、ディルムッドの知る彼女の名であるらしい。自身にとってはまったく聞き覚えのない名前だった。しかし彼は、至上の幸福といった表情で彼女をそう呼んだ。大切そうに、その単語の持つ響きごと尊ぶように。 「俺は、あの時のことを心から悔いています。あなたをお守りすると誓ったにもかかわらず、その命を最後まで守りきることが出来なかった。聖杯をあなたの手に捧ぐことも、―――そしてあなたと共に生きることもです。俺にとって、あなたはすべてだったのに」 は、ディルムッドの発する言葉を何一つ理解できなかったが、ただ息を潜めて、次の言葉を待つしか術がなかった。 「あの図書館で"すべて"を知った時、俺はまず、最期のあなたの言葉を思い出しました。…あなたは死の直前にこう仰られた。『死んでもまた巡り合いたい』と。だから、俺は誓ったのです。たとえこの身が朽ちようと、幾度生まれ変わろうと、必ずあなたのことを見つけ出すと。俺が、この世界で、こうしてふたたびあなたを見つけ出せたことは、運命だったんです。この世に生を受けて、あなたを今度こそ幸せに出来ると思った」 決して嘘偽りのない本心なのだろう。彼の眉間に寄せられた皺や、固く強張った拳が、切にそう訴えていた。 「……忘れているなら、思い出すまで待ちましょう。あの約束が、簡単に葬られていいはずがないのです」 ディルムッドは突然身を屈め、の足元に跪いた。そして彼女が声を上げる間も与えずに、彼女の膝にそっと触れる。つい先ほどまで全身から放っていた狂気とは裏腹に、とても優しい手つきだった。怯えたが必死に身を引こうとするも、彼の大きな手のひらが彼女の足をしっかりと捕まえるので、身じろぎさえもままならなかった。 彼は、の右膝をじっと見つめている。そこには、つい先刻転んだ際にすりむいた傷跡があり、僅かながら血も滲んでいた。恐怖で忘れかけていた痛みが、今さらながら彼女の神経をじくじくと痛めつける。 「痛いですか?」 「……っ」 「相変わらず、気丈なお方だ」 そう言って、彼は目の前にある傷口にそっと口づけた。舌がちろりと這う感覚に、は思わず顔を歪める。 「…あなたは、」 もはやそれは涙声に等しかった。彼女の心には、この男から逃れる手はないのだという、やるせない絶望だけが満ちている。クモの糸にかけられた蝶の如く、逃げ場などどこにも見つけることができなかった。 「あなたは、何が望みなの?」 ディルムッド、とは決して呼ばなかった。呼べなかったのだ。その名前を呼んでしまえばもう、本当に、二度と元の世界に戻れなくなるような気がして。 「××殿。―――愛しい我が主よ」 ディルムッドは慈愛に満ちた表情で彼女を見上げている。何も語らずとも、そのまなざしは、彼女への慕情を雄弁に物語っていた。 「あの世界での続きをしましょう」 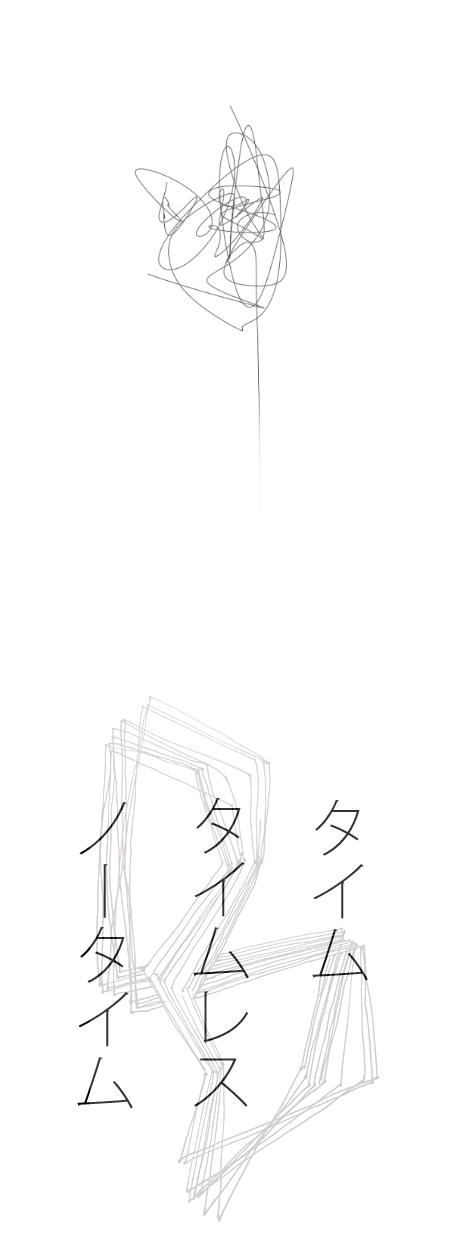
マイフレンドむぎさんへ捧げます。エセディルムッドでごめんね。でも頑張ったのでご褒美に月島くんください。 タイトルはウォルター・デ・マリア氏の作品より。 あの空間の持つ圧倒的な非現実感を描きたかったです。ムリでした。(撃沈しました) また、舞台は清春芸術村の光の美術館、直島の地中美術館からイメージを。 安藤忠雄氏が作り出すあの無機質な雰囲気が大好きです。 2014.09.10 |